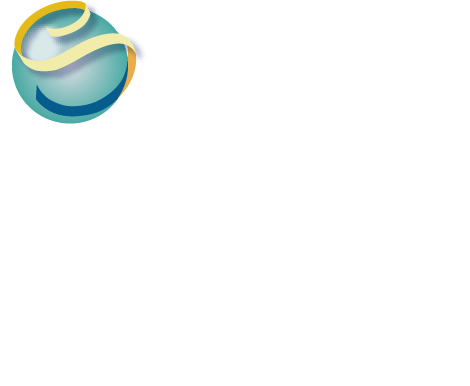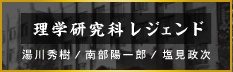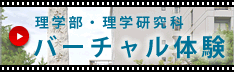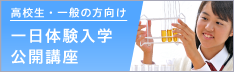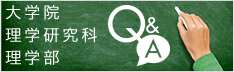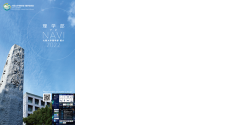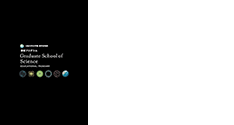月面観測が「銀河宇宙線」の謎を解く可能性
-次世代MeVガンマ線天文学が異分野連携で新展開へ-
大阪大学大学院理学研究科の藤原立貴さん(博士後期課程)、井上芳幸准教授らの研究チームは、次世代のMeVガンマ線望遠鏡を用いて月を観測することで、これまで未開拓だったMeV銀河宇宙線スペクトルの測定が期待できることを理論計算により示しました。
銀河宇宙線は、発見から100年以上経過した現在でも起源が明らかにされていません。なかでも、「宇宙に存在するプラズマがどのようにして銀河宇宙線まで加速されるのか」という問いは、宇宙線研究における最大の謎の一つとされています。この問題を解く鍵となるのが、最低エネルギー帯に属するMeV銀河宇宙線の性質を明らかにすることです。しかし、MeV銀河宇宙線は高エネルギー宇宙線に比べて太陽磁場や地磁気の影響を受けやすく、これまで地球周辺で直接観測することができませんでした。
今回、研究チームは、銀河宇宙線が月面物質と原子核反応(衝突)して生じるガンマ線放射現象に着目しました。このようなガンマ線を観測することで、反応の起源になった銀河宇宙線のスペクトルを間接的に知ることができるのです。従来の望遠鏡では、低エネルギー宇宙線の月面核反応に由来するMeVガンマ線を詳細に捉えることはできませんでした。そのため、月を用いたMeV銀河宇宙線の観測に関心は集まっていませんでした。しかし今回、研究チームは銀河宇宙線と月面物質との原子核反応により生じるMeVガンマ線スペクトルを理論的に計算し、次世代の高性能なMeVガンマ線望遠鏡を用いることでその観測が可能であることを示しました。特に本研究では、MeVガンマ線に特有の核ガンマ線を観測することで、MeV銀河宇宙線の百万年スケールにわたる長期変動を調べられる可能性も示しました。この成果により、地球からMeV銀河宇宙線を間接的に観測する新たな方法を提示するとともに、銀河宇宙線の起源解明に向けた一歩となることが期待されます。
本研究成果は、米国科学誌「The Astrophysical Journal」に、7月8日(火)17時(日本時間)に公開されました。

ガンマ線(> 30 MeV)で見た月。黄色に近いほど宇宙線の衝突により明るい。
(Credit: NASA/DOE/Fermi LAT Collaborationより改変)
Related links
本件に関する問い合わせ先
大阪大学 大学院理学研究科 宇宙地球科学専攻
准教授 井上 芳幸(いのうえ よしゆき)
E-mail: yoshiyuki.inoue.sci@osaka-u.ac.jp
藤原 立貴(ふじわら たつき)
E-mail: u000719k@ecs.osaka-u.ac.jp