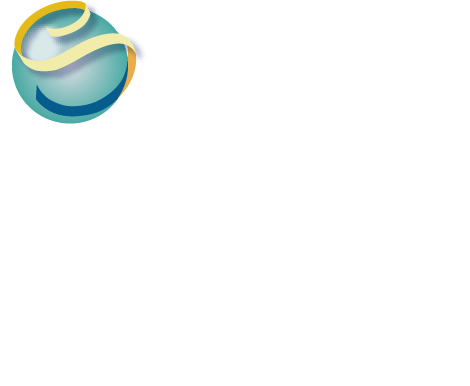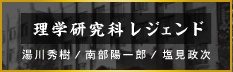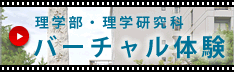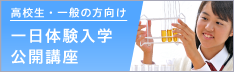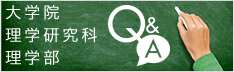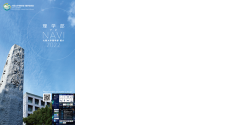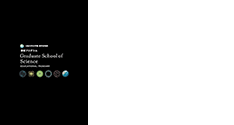メッセージ
大阪大学は地元財界の全面的な財政的支援を受け、昭和6年(1931年)に国内で6番目の帝国大学として創設されました。当初は、医学部と理学部の2学部でしたが、昭和8年(1933年)に工学部を加え、3学部からなる総合大学となりました。初代総長は、土星型原子模型を提唱したことで有名な物理学者の長岡半太郎博士であり、研究第一主義を掲げ、漆の研究で有名な眞島利行理学部長の下、代数学の正田健次郎、八木アンテナを発明した八木秀次、X線構造解析の仁田勇、原子物理学の菊池正士などの諸先生が集い、若々しい理学部の活発な研究を支えました。その後、まだ学位取得前の湯川秀樹氏が講師として加わり、中間子論の研究を進めて本学で博士号を取得されました。まさにその時の研究成果が、後に、日本初のノーベル賞に輝いたのです。以来、理学部は『勿嘗糟粕(そうはくをなむるなかれ)』という長岡半太郎博士の言葉を精神的規範とし、世界に先駆けた独創的な研究と教育を続けています。

近藤 忠

「勿嘗糟粕」 糟粕(そうはく)を嘗(な)むる勿(なか)れと読み、
“ つねに創造的であれ” といった意味である。
現在の理学研究科・理学部は、6専攻4学科からなり、約 200 名の専任教員、約 1200 名の学部学生、約 900 名の大学院生を擁し、大阪大学の中でも中核的な部局の一つです。平成 16 年度 (2004 年度 ) の国立大学法人化の際には、迅速な意思決定を行うべく、それまでの教授会の機能の一部を、専攻長・学科長合同会議で代行することを決めました。また、研究科長と教育・研究・運営を担う6 名の副研究科長及び事務長などからなる企画調整会議を組織し、研究科のさまざまな企画や予算運用などについての立案を行っています。
令和4年 (2022 年 )には、大型のプロジェクト研究を推進する基盤的役割を果たしてきた『基礎理学プロジェクト研究センター(PRC)』を発展的に改組して『フォアフロント研究センター(FRC)』を設立し、専攻や研究科などの従来の枠組みを超えた分野横断型プロジェクトや産学連携研究を推進する場を提供するとともに、若手研究者が挑戦的な研究を徹底的に推進する機会を与え、将来的にノーベル賞級の独創的基礎研究を生み出せるような研究環境の整備を行っています。また、FRCの研究活動拠点となる建物(理学 J 棟)の2階にある南部陽一郎ホールでは、公開講座であるサイエンスナイトをはじめとする社会連携を図るさまざまな企画を実施しており、理学研究の成果を開かれたものとする活動が展開されています。
自然界に見え隠れする理(ことわり)を明らかにする「理学」という学問分野の歴史は長く、人類がこれまで蓄積した知や技術の先にあるフロンティアを常に探求して、これまでも新たなる真理の発見と新しい概念の構築に貢献してきました。最先端の科学技術の発展に伴う大きな社会変革や、世界的規模となっている自然界の環境変化が進む現在においては、科学の基盤となる理学を学び、人類社会の発展に貢献していく意義と責任はこれまで以上に重くなっていると感じます。最先端研究の多くでは、高校で学ぶ理科のような分野の境界は曖昧となっており、時に工学的要素も含めながら既存の研究分野が協力・融合した新たなテーマの学術研究が日々進行しています。日常の小さな疑問や純粋な興味から始まった研究成果が、社会に役立つ技術に発展した例は、枚挙にいとまがありません。理学はすべての科学を育むための「根源となる泉」のような存在であるとも言えます。人々の内面にも、また地球外にまで世界観が広がってきている今こそ、自然界の不思議に目を向け、その謎解きに真剣に取り組むという理学の精神を、理学部・理学研究科のすべての教員と学生が共有し、未来に発展的に引き継いでいきたいと思います。